「展示」という問いかけ ―『After all』をめぐるキュレーターの記録 文:後藤由美
 先日開催されたトークイベントにて、キュレーターとして「展示空間」と鑑賞者との関係性についてお話しさせていただきました。その際に共有した考察の一部を、あらためてここに綴ります。
先日開催されたトークイベントにて、キュレーターとして「展示空間」と鑑賞者との関係性についてお話しさせていただきました。その際に共有した考察の一部を、あらためてここに綴ります。
写真作品における「見る」という行為を、身体、思考、記憶を巻き込んだ空間体験としてどう構成しうるか——。
展示設計とキュレーションの交差点で立ち上がってきた問いと試みを、記録として残しておきたいと思います。
【After all トークイベント|2025年5月3日】
本日は、展示空間そのものがどのように鑑賞者の身体や記憶、感情に作用していくのか。 その関係性について、お話ししたいと思います。この展示では、写真作品の内容と並行して、空間そのものの設計にも強い意識が注がれています。 私たちは、「見る」という行為を、単なる視覚情報の受容ではなく、身体を伴った全方位的な体験として捉えています。 鑑賞者が空間を移動し、立ち位置や視点を変えることで、同じ作品であってもまったく異なる印象が立ち上がる。 そうした視覚と身体が交差する場として、展示空間が機能することを目指しました。
 会場には、千賀と林田による写真を配し、高さや奥行きが異なる構造を設け、視線が自然と斜めに導かれたり、それぞれの作品の関係性や被写体の力関係が再認識されたりするよう設計されています。 ある位置からは見えていたものが、数歩移動すると隠れたり、逆に開かれたりする。 作品を「見る」ことが、作品に「導かれる」ことでもあるような構成です。
会場には、千賀と林田による写真を配し、高さや奥行きが異なる構造を設け、視線が自然と斜めに導かれたり、それぞれの作品の関係性や被写体の力関係が再認識されたりするよう設計されています。 ある位置からは見えていたものが、数歩移動すると隠れたり、逆に開かれたりする。 作品を「見る」ことが、作品に「導かれる」ことでもあるような構成です。

 一角には象徴的な「未来は今我々が何をするかにかかっている」という文言が、無機質な等身大の室内に掲げられているのが確認できます。 日常の中でよく目にするような、耳障りのよいこの言葉は、展示の文脈に置かれることで、別の意味を帯び始めます。 これらは一見もっともらしいですが、社会的に内面化された“正しさ”が、実は個々人の価値判断をどのように規定しているかを問い直す装置として機能しています。
一角には象徴的な「未来は今我々が何をするかにかかっている」という文言が、無機質な等身大の室内に掲げられているのが確認できます。 日常の中でよく目にするような、耳障りのよいこの言葉は、展示の文脈に置かれることで、別の意味を帯び始めます。 これらは一見もっともらしいですが、社会的に内面化された“正しさ”が、実は個々人の価値判断をどのように規定しているかを問い直す装置として機能しています。
 千賀が二階に設置した物理的な装置からは、こうした社会に溢れる常套句や、行動を促す言葉たちが、アスキーアートで表された顔とともに不気味に垂れ流されるレシート状に印刷され、観客に繰り返し差し出されます。 人が金銭的・数値的価値で消費される構造や、メッセージの無限反復が持つ暴力性を、遊びのような形式で可視化しています。
千賀が二階に設置した物理的な装置からは、こうした社会に溢れる常套句や、行動を促す言葉たちが、アスキーアートで表された顔とともに不気味に垂れ流されるレシート状に印刷され、観客に繰り返し差し出されます。 人が金銭的・数値的価値で消費される構造や、メッセージの無限反復が持つ暴力性を、遊びのような形式で可視化しています。
この展示では、写真をただ壁に並べて見せるのではなく、空間そのものが作品の一部として機能しています。 鑑賞者が身体を使って動くことで、初めて作品の意味が立ち上がってくる。 静的なメディアである写真が、空間や身体を介して、時間性と体験の厚みを帯びてくる。 そうした設計を意図しました。
また、来場者の一人からは、奥に設置されたインスタレーションについて「整然と配置されているようでいて、どこか一種の不法投棄のようにも見える」という印象が寄せられました。 これは、展示空間における秩序と混沌、可視と不可視の間を揺らぐ感覚を、私たちが意図した以上に繊細に感じ取った反応だと言えるかもしれません。二人の作品から、日本の裏社会のビジネスモデルが時代を経てシフトしていき、新たなものに飲み込まれていく様子まで想像していただけるといいと思います。
二人の作品は全国の不法投棄と特殊詐欺を扱ったものであり、入口が不法投棄で段々と特殊詐欺に移り変わるという展示構成になっています。 一見すると、千賀の展示かと誤解されやすい構成ですが、実際には写真の枚数でいうと、仮設壁:林田2枚、千賀3枚、吹き抜け:林田25枚、千賀23枚、2階:林田33枚、千賀21枚となっています。 つまり、サイズが小さいだけで、それは不法投棄の規模が縮小していることを表し、千賀が展示をジャックしているかのように見える――ある種、詐欺的な構成が展開されている、という仕掛けになっています。
 展示は、鑑賞者がその空間のなかで、ただ受け取るのではなく、自身の身体や感覚、記憶を通じて意味を再構築していくという体験です。 展示空間は、作品を一方的に「見せる」のではなく、鑑賞者が能動的に「見る」という行為そのものに関わる場である。 視覚だけでなく、身体、思考、感情のすべてが関与する場としての展示空間。 その中で、観客が意味を受け取るだけでなく、自らの記憶や感覚を通じて意味を構築していく——そうした能動的な「見ること」のあり方が、この展示の根底に流れています。
展示は、鑑賞者がその空間のなかで、ただ受け取るのではなく、自身の身体や感覚、記憶を通じて意味を再構築していくという体験です。 展示空間は、作品を一方的に「見せる」のではなく、鑑賞者が能動的に「見る」という行為そのものに関わる場である。 視覚だけでなく、身体、思考、感情のすべてが関与する場としての展示空間。 その中で、観客が意味を受け取るだけでなく、自らの記憶や感覚を通じて意味を構築していく——そうした能動的な「見ること」のあり方が、この展示の根底に流れています。
今回の展示を準備していくなかで、あるご指摘を受けたことをきっかけに、結果的に出会うことになった示唆的な論文があります。 ブラジルの研究者レナータ・ペリム・ロペスによる「Exhibition Design and the Relationship With the Spectator」という論考で、20世紀初頭に活躍したエル・リシツキーやヘルベルト・バイヤーが、展覧会デザインにおいて“観客との関係”をどのように考えていたかを丁寧に掘り下げています。
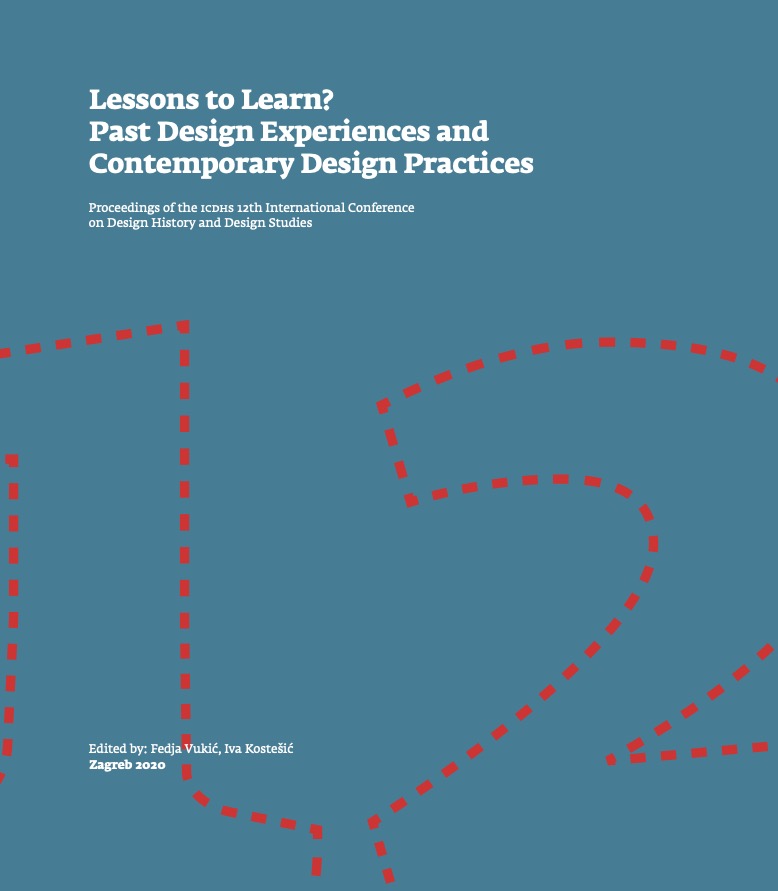 この論文を読んで改めて思ったのは、「展示空間って、“見る場所”だけじゃないんだな」ということです。 リシツキーやバイヤーは、視覚だけに頼るのではなく、身体を動かしたり、触れたり、音に気づいたりする——そういう「五感で関与する」場として展示を捉えていました。 たとえばバイヤーは「視野のフィールド」という概念を提唱していて、観客がただ立ち止まって見るのではなく、自分の体の動きや位置によって作品との関係が変わる、という空間を作っていました。
この論文を読んで改めて思ったのは、「展示空間って、“見る場所”だけじゃないんだな」ということです。 リシツキーやバイヤーは、視覚だけに頼るのではなく、身体を動かしたり、触れたり、音に気づいたりする——そういう「五感で関与する」場として展示を捉えていました。 たとえばバイヤーは「視野のフィールド」という概念を提唱していて、観客がただ立ち止まって見るのではなく、自分の体の動きや位置によって作品との関係が変わる、という空間を作っていました。
その考え方は、私たちの今回の展示構成にも通じるものがあるように思います。作品の見え方が、順路によって変わるように設計しています。 また、展示を組み立てていく過程では、単に作品を並べるだけではなく、「どう見せるか」「どこに置くか」といったデザインの部分とキュレーションが密接に結びついていきました。 この論文でも、展示デザインはキュレーションと対話しながら意味を構成していくべきだ、とあり、それはまさに今回のプロセスと重なるところです。 そして最後にとても印象的だったのが、「展示空間はその時代の文化コードを反映している」という指摘です。 今私たちがこの場に展示を構成するということも、2020年代という時代の空気——不確実性だったり、再接続への欲求だったり、あるいは触れることの意味の変化だったり——そうしたものと無縁ではないんだな、と感じています。
構成・執筆:後藤由美(RPS京都分室パプロルキュレーター)
展覧会情報
タイトル| After all
作家| 千賀健史、林田真季
会場| RPS京都分室パプロル(京都市上京区老松町603)
会期| 2025年4月12日(土)– 5月11日(日)
開場時間| 13:00 – 19:00
入場料| 無料
